妊娠初期に感じる症状とは?発生する時期や注意すべき行動も解説

記事監修者:助産師 坂田陽子 先生
助産師/看護師/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー

「初めての妊娠で不安」
「どのような症状が起きるの?」
「妊娠初期はどのようなことに気をつけるべき?」
と心配になっていませんか。
初めての妊娠はわからないことが多く、先行きも不安になりますよね。
妊娠初期は「微熱」「匂いに敏感になる」などの症状を感じて、妊娠に気付くケースが多いです。
また妊娠が進むと、つわりが始まり「眠気」「胃痛」などの症状も感じる場合もありますが、対処法はあります。
この記事では、おもに以下の内容を解説していきます。
・妊娠初期症状と対策
・妊娠初期症状を引き起こす3つのホルモン
・妊娠初期の禁止行動
この記事を読むと、妊娠初期に起こる症状がわかり、安心して妊娠生活を遅れるようになりますよ。
そもそも妊娠初期とは?

厚生労働省が公開している日本産婦人科学会の資料によると「妊娠0〜13週」までが妊娠初期と定義されています(※1)。
妊娠初期は子宮に到達した受精卵が子宮内膜に着床し、妊娠が成立した直後の段階です。
妊娠週数の数え方は、最終月経(直近の生理日)の初日を「妊娠0週0日」としてカウントします。
つまり妊娠前から、妊娠週数を数え始めるのです。
「妊娠週数を数えるのが面倒」という人は、厚生労働省が提供している下記の自動計算ツールで算出してみましょう。
厚生労働省委託 働く女性の心とからだの応援サイト「いつ、何に気をつければいい?妊娠週数・月数の自動計算」
なお順天堂大学医学部附属静岡病院産 婦人科が公開している資料によると、妊娠4週未満を「妊娠超初期」と呼ぶケースもあります(※2)。
妊娠超初期は卵子と精子が受精し着床する期間で、まだ妊娠が確認できない期間です。
出典
(※2)順天堂大学医学部附属静岡病院 産婦人科「妊娠中の薬について」
【発生割合順】妊娠初期に感じた症状

妊娠初期は微熱が続いたり、匂いに敏感になったりなど、つわりと呼ばれるさまざまな症状が現れます。
株式会社ゼネラルリンクが妊娠経験のある女性を対象に行った調査結果によると、妊娠初期に感じた症状とその割合は以下のとおりでした。
| 症状 | 割合 |
| 微熱 | 32.1% |
| 匂いに敏感 | 27.8% |
| 眠気 | 26.7% |
| 胃痛・胸やけ | 23.5% |
| 乳房への違和感 | 22.7% |
| 風邪のような症状 | 15.5% |
| おりものの変化 | 13.6% |
| 生理前のような精神状態 | 9.4% |
| 腹痛 | 8.6% |
| 腰痛 | 7.8% |
| 便秘・下痢 | 7.5% |
| 頻尿 | 6.4% |
| 唾液の増加 | 2.1% |
出典:株式会社ゼネラルリンク「妊娠初期症状・つわりに関する調査!76.8%は「日常生活に支障がある」【赤ちゃんの部屋】」より抜粋して作成
なかでも眠気や胃痛・腹痛などは、とくにつらい症状ですが、対処法はあります。
気になる人は下記も参考にしてくださいね。
▼妊娠初期の眠気対策
▼妊娠初期の胃痛対策
▼妊娠初期の腹痛対策
妊娠初期症状は5~6週に現れる

5〜6週に妊娠初期症状(つわり)が始まり、8~10週に症状のピークを迎え、16 週頃に消失していくといわれています(※3)。
実際に、株式会社エムティーアイが運営するルナルナが行ったアンケート調査によると、妊婦さんの約70%が「妊娠16〜19週」までに、つわりが落ち着いたと回答しました(※4)。
一方で、妊娠初期症状を感じないケースもあります。
実際、株式会社ゼネラルリンクが行ったアンケート調査によると「約15%」の人はつわりの経験がないと回答していました(※5)。
ただしほとんどの妊婦さんはつわりを経験するため、対策は必要だといえるでしょう。
出典
(※3)東京山手メディカルセンター 産婦人科 「ママノート②妊娠中に起こりやすい病気と生活の注意点について」
(※5)株式会社ゼネラルリンク「妊娠初期症状・つわりに関する調査!76.8%は「日常生活に支障がある」【赤ちゃんの部屋】」
妊娠初期症状を引き起こす3つのホルモン
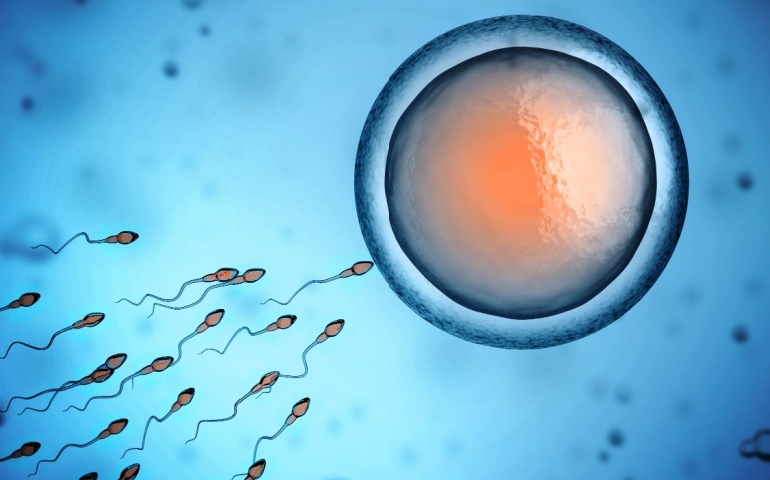
妊娠を期に以下3つのホルモンが分泌されやすくなり、妊娠初期症状が引き起こされます。
・hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)
・エストロゲン(卵胞ホルモン)
・プロゲステロン(黄体ホルモン)
順番に解説していきます。
1:hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)
胎盤の絨毛という組織から分泌されるホルモンで、妊娠中だけ分泌量が活発になります。
hCGはのちに紹介する「プロゲステロン(黄体ホルモン)」と呼ばれるホルモンの産生を促し、妊娠6〜8週までの妊娠を維持するのです(※6)。
また着床するタイミングで尿中に出てきます。
妊娠検査薬では尿中に含まれるこのhCGを測量して、妊娠の結果を判定しているのです。
出典(※6)東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部「妊娠検査薬で妊娠判定が出来るのはなぜ?—hCGについて—」
2:プロゲステロン(黄体ホルモン)
プロゲステロンは「妊娠を成立・継続」させるホルモンです。
のちに紹介する「エストロゲン(卵胞ホルモン)」の働きによって、厚くなった子宮内膜を柔らかく維持して妊娠しやすい状態にします。
ほかにも水分や栄養素をため込んで妊娠を維持したり、体温を上げたりする働きがあるのです。
一方でむくみや食欲増加、イライラ、眠気などが起こりやすくなります。
3:エストロゲン(卵胞ホルモン)
妊娠の準備をするホルモンです。
卵巣内の卵胞を成熟させて排卵に備えたり、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を厚くしたりします。
また丸みのある体、乳房の発育など女性らしい体をつくる働きがあります。
ほかにもコラーゲン生成を促して美肌をつくったり、骨・脳・血管・関節などを健康に保つ役割もあるのです。
注意!妊娠初期の禁止行動

妊娠初期は胎児の臓器や組織がつくられていく重要な時期です。
そのような大事な時期に「飲酒」「喫煙」などを行うと、流産するリスクが高まります。
たとえば喫煙を例にすると、喫煙者から生まれた赤ちゃんは、非喫煙者から生まれた赤ちゃんに比べて「低出生体重児」となる頻度が約2倍も高くなると厚生労働省によって報告されているのです(※7)。
また早産、自然流産のリスクも高まるといわれています。
一方で妊娠初期に喫煙していても「妊娠3〜4か月」までに禁煙すれば、低体重児出生の可能性や早産などのリスクは下がるといわれています(※8)。
いま喫煙しているからといって遅いと思わず、いまこの瞬間から禁煙しましょう。
喫煙以外にも、妊娠初期に控えたほうがよい行動はさまざまあります。
下記の記事では妊娠初期にやってはいけない行動について解説しています。
妊娠初期を安全に過ごすためにも参考にしてみてくださいね。
出典
(※8)公益財団法人 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター「妊産婦への禁煙サポートの必要性」
妊娠初期にとるべき!6つの栄養素

妊娠初期はつわりが始まる頃でもあり、食事をとりづらい時期でもありますが、自身や胎児のために栄養補給が欠かせません。
なかでも以下6つは、積極的にとりたい栄養素です。
・たんぱく質
・葉酸
・鉄
・カルシウム
・ビタミンD
・食物繊維
これらの栄養素は自身や胎児の体調を整え、健康な発育を促します。
ただし無理に食べようとせず、自身の体調にあわせて食べられそうなものを食べられるタイミングでとりましょう。
以下の記事では各栄養素について、さらにくわしく解説しています。
おすすめのレシピも公開しているため、ぜひ参考にしてくださいね。
妊娠初期のQ&A

妊娠初期について、よくある3つの質問をまとめました。
順番に見ていきましょう。
Q1:性行為はしてもよい?
胎盤が未完成である妊娠初期での性行為は避けましょう。
性行為による刺激や精液による子宮収縮、細菌感染症などにより、流産・早産の原因となる可能性があります。
Q2:腹痛や頭痛時に市販薬は使用してもよい?
自己判断で医薬品は服用しないようにしましょう。
一方で、これまで継続して服用してきた医薬品を自己判断でやめる行為も危険です。
医薬品の服用、もしくは服用中止で胎児や母体に悪影響を与えるからです。
医薬品の服用・中止については、医師に相談して判断を委ねましょう。
Q3:妊娠初期運動はしてもよい?
妊娠前は運動が日課だった妊婦さんもいるのではないでしょうか。
しかし妊娠初期は「ダッシュ」「階段の昇降」など心拍数を上げる激しい運動や、おなかに力を入れたり、圧迫されたりする腹筋や背筋も避けましょう。
いずれも胎児に影響を与える可能性があります。
一方、妊娠初期に行う運動には「適性体重の維持が可能」「ストレス解消できる」などメリットも存在します。
下記の記事では、妊娠初期に運動を行う4つのメリットや具体的な運動例も紹介しています。
「妊娠初期も運動したい」「これから運動をとり入れようか考えている」という人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
まとめ
妊娠初期は「妊娠0〜13週」までをさし、「5〜6週頃」にはほとんどの妊婦さんが初期症状を感じ始めます。
妊娠初期症状は、以下3種類のホルモンが分泌されやすくなるために起こります。
・hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)
・エストロゲン(卵胞ホルモン)
・プロゲステロン(黄体ホルモン)
個人によって症状はさまざまですが、眠気や胃痛などを感じたりする場合が多いでしょう。
妊娠初期は胎児の様態が不安定なため、行動や食事には十分な注意が必要です。
今回紹介した内容を参考にして、母子ともに健康な生活を送り、出産に備えてくださいね。
胎児が育っていく様子を知りたい人は、下記も参考にしてみてください。
妊娠週数別に胎児の成長過程を紹介しているため、あなたの赤ちゃんがどれくらい育っているのかわかるようになりますよ。
赤ちゃんの未来に備える「さい帯・さい帯血保管」を考えてみませんか?
赤ちゃんとお母さんをつなぐ、「へその緒(さい帯)」と、その中を流れる血液「さい帯血」には、体を作るためのもととなる貴重な「幹細胞」が多く含まれていて、赤ちゃんやご家族の将来に備えて長期的に凍結保管することができます。
幹細胞は新しい医療への活用が進められており、もしもの時に役立てられる可能性があります。
- 出産後わずか数分の間にしか採取できない貴重な赤ちゃんのものです。
- 採取の際、お母さんと赤ちゃんに痛みや危険はありません。
- どちらにも幹細胞がたくさん含まれています。
- 再生医療分野など、さまざまな活用が進んでいます。
- それぞれ異なる幹細胞が含まれているため、両方を保管しておくことで将来の利用の選択肢が広がります。
実際に保管・利用した方のお声
出産時にしか採取できない「さい帯血」を、脳性まひのお子さまに対して臨床研究で使用された方のお声をご紹介します。

高知大学の臨床研究で
さい帯血投与を受けたお子さま
さい帯血を保管して
本当に良かったと思っています
元気に産まれたと思っていましたが、生後半年頃から左手をほとんど使おうとしないことに気付き、1歳頃にやはり何かおかしいと思ってMRIを撮ってもらうことにしました。結果1歳5ヶ月で脳性まひとわかりました。
2歳の誕生日にステムセルからハガキが届き、出産時に保管したさい帯血がもしや役に立つのではと思い至りステムセルに問い合わせました。ちょうど臨床試験への参加者を募集していて、運よく2歳5ヶ月のときに参加することができました。
輸血前は左手と左足に麻痺があり、歩けてはいるものの、とても転びやすく、少し歩いては転びを繰り返していました。しかし輸血後、翌日には転ぶ回数が減り、おもちゃを両手で掴めるようになって驚きました。その後もリハビリも継続し、完治したわけではありませんがかなり麻痺が軽くなったように思います。
現在、地域の小学校の普通級に集団登校で通えています。
まさか我が子がさい帯血を使って治療をすることになるとは思っていませんでしたが、保険のつもりでさい帯血を保管しておいて本当に良かったと思います。
さい帯・さい帯血を利用した再生医療の研究が、今まさに国内外で進んでいます。
その他のお声は公式サイトからご覧いただけます。
医師からのメッセージ

総合母子保健センター
愛育病院 病院長
百枝幹雄 先生
応用範囲が広がる
「さい帯・さい帯血」による再生医療
近年、めざましく進歩している再生医療のなかで、さい帯やさい帯血の幹細胞を利用する技術の最大の特徴は、通常は破棄してしまうけれども実はとてもポテンシャルの高い出生時の幹細胞を活用するという点です。
これまで有効性が示されている白血病、脳性まひ、自閉症のほかにも様々な疾患に対して臨床研究が進んでいますし、民間のバンクではご家族への利用も可能になりつつありますので、今後はますます応用範囲が広がることが期待されます。
一方、忘れてはならないのは必要になるまで幹細胞を長期間安全に保管するには信頼できる設備と技術が必要だということで、それにはそれなりのコストがかかります。
コスト・ベネフィットのとらえ方は人それぞれですが、お子様とご家族の将来を見据えてベネフィットが大きいとお考えの方には、信頼できる施設へのさい帯やさい帯血の保管は十分価値のある選択肢だと思います。
さい帯・さい帯血についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
保管するなら、ステムセル研究所の「HOPECELL(ホープセル)」
株式会社ステムセル研究所が提供する「さい帯・さい帯血ファミリーバンクHOPECELL(ホープセル)」は、日本国内で最も選ばれている保管サービスです。
ステムセル研究所は、25年以上の保管・運営実績がある日本初のさい帯血バンクで、国内最多となる累計80,000名以上のさい帯血を保管しています。


研究所

研究所
国内では脳性まひに対する、赤ちゃんご自身やごきょうだいのさい帯血投与の研究が行われています。海外の臨床研究では、投与により運動機能および脳神経回路の改善が報告されています。また自閉症スペクトラム障害(ASD)に対して、さい帯血の投与によりコミュニケーション能力や社会への順応性が向上する可能性が期待されており、大阪公立大学にてお子さまご自身のさい帯血を投与する臨床研究が開始されます。

研究所
無料パンフレットをお送りします!
さい帯・さい帯血保管についてより詳しく知っていただけるパンフレットをご自宅へお送りします。
赤ちゃんの将来に備える「さい帯・さい帯血保管」をぜひ妊娠中にご検討ください。

この記事の監修者
助産師 坂田陽子 先生
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー
















